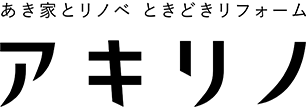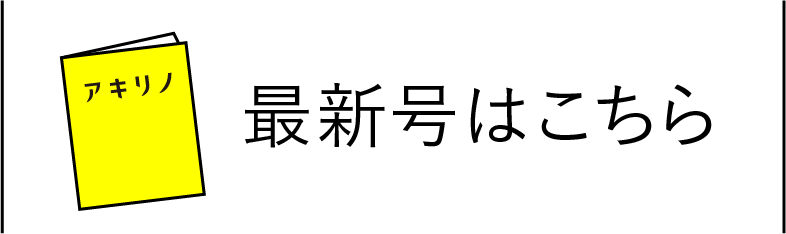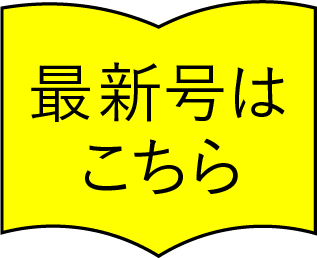新着情報

陶芸家ユニット 手島に暮らすvol.14
アキリノcolumnは、京都から香川県丸亀市の離島、手島に移住してきた陶芸家、松下龍平さんに古民家のDIY体験談を思いのままに綴ってもらう新企画です。どうぞお楽しみください。

文/写真 松下龍平
一緒に陶芸活動をしている松原恵美さんと、2019年春に瀬戸内海の離島、手島に移住。自分たちで古民家を改修しながら、「てしま島苑」の名で陶芸活動をしている。海岸の土や収穫後の野菜の残渣(ざんさ)、見頃の終わった向日葵など、島の素材だけを使ったやきもの “手島焼き” を制作している。住まいの他にギャラリーや工房スペースも改修中。
___________________________
前回は水回り小屋の壁の骨組みを立ち上げました。今回はトラス構造での屋根づくりをお話していきます。
トラス構造は木材等で三角形をつくり、それを組み合わせて構成する構造の事で、橋やアリーナによく使用されています。鋭角な三角形を2つ組み合わせ、開いたコンパスのような形のものを9個つくり、前回立ち上げた壁に渡して固定していきます。
この時はまだ暑さの残る10月頃でした。ここから、屋外作業は特に辛い島の冬がやってきます。手島の冬は、実家のある埼玉では感じた事のない厳しい冬です。気温と海水温の差からくるのか、1日中台風並の強風が続きます、時には2日続けて船が欠航する事もある程です。
そんな中で、次に待ち受けているのが屋根の作業でした。トラス構造部に、合板を打ちつけ、その上に遮熱性のある透湿防水シートを貼り、ガルバリウムの波板を打ちます。行なっている作業は、壁と似たような内容ですが、それが冬の時期の屋根作業となると、あんなにも辛いものになるとは思ってもいませんでした。悴む手と脚、涙と鼻水がとまらない中での作業です。更には、屋根であるが故に気をつけなければいけないポイント(雨仕舞いや、湿気を抜く為の通気口等)や、ここでも立ちはだかる既存の建物との接続部等、本当にわからない事だらけでした。いつも助けてもらっている友人
も屋根作業はした事がないらしく、どうしたら良いのか途方にくれたまま終わった日もありました。大工さんのYouTubeやネットを漁り、なんとかつくり終え、今でも雨漏りや木の腐食もなく暮らせています。
その後、お風呂やトイレ、洗面所の部材を調達し、自分達で組み立て、2年半かけようやく快適に暮らせる”家”が出来上がりました。
次回はこれまでのことを振り返っていきたいと思います。

次回、陶芸家ユニット手島に暮らすvol.15 は、3月末発行のアキリノstories015でもご覧いただけます。
てしま島苑 Instagram